2019年11月05日の心の糧

わたしが抱く平和
服部 剛
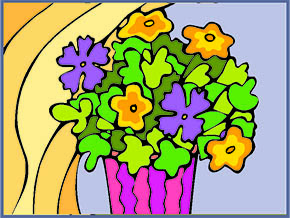
最近、先輩に勧められ、第2次大戦中、陸軍に看護婦として従軍した阿武千代さんの手記、「陸軍看護婦」を読みました。戦時中の中国に派遣され、日々運ばれる負傷兵の手当てをする著者の真摯な姿と優しい人柄が行間から伝わり、〈私はこの人のような愛を生きることができるだろうか?〉と自分に問いました。
著者の生き方で、特に心に残ったのは、どんな状況においても希望を失わず、深いまなざしで日々出逢う一人ひとりをみつめていたことです。赤痢で亡くなった兵士の体を母親のように抱きながら拭く看護婦の先輩、仕事が上手くいかず沈んでいたときに温かい声をかけてくれた軍隊長、マラリアに倒れたときにそっとパンを届けてくれた同僚... 過酷な戦火を生きる人々の心ある姿が目に浮かびました。
やがて終戦を迎え、中国から引き揚げる直前の兵営内では文化祭が行われ、著者は趣味の生け花を出品しました。その前向きな姿勢から、人間が生きがいをもつことの豊かさを感じました。演芸大会では手作りのギターや笛等の演奏が人々の心を潤し、引揚船のなかでは、ようやく日本へ帰ることのできる安堵と、外地での疲れ果てた人々をねぎらうために吹かれたハーモニカの音色が沁み入る様子が描かれています。それらの場面から、私は「音楽や芸術の存在意義」を思いました。
終戦から70年以上の歳月は流れ、令和の時代になりました。戦争体験を語り継ぐ人が減ってゆくなかで、陸軍看護婦の手記が語っていることは、戦争の悲惨さ、理不尽さ、それに翻弄される人々の有り様、そして平和の尊さです。
この本の最後に著者が語る「与えられた人生の一日をいかに受け取り、生きるかが大切です」というメッセージに私は今、想いを巡らせています。