2019年08月08日の心の糧

母のぬくもり
堀 妙子
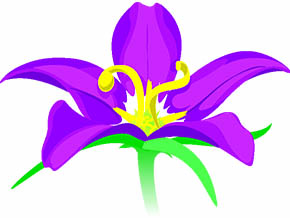
母が天のふるさとに帰ってからもうすぐ4年経つ。
母は和紙をとじた小さな「御言葉手帖」に好きな御言葉を綴っていた。今まで気づかなかったのだが、この手帖に、4つにたたんだ和紙がはさんであった。それは「幻の影を追いて」という讃美歌が母の字で丁寧に写されていた。1番から4番まであり、どれも心を打つ歌詞だが、2番と4番の一部を読んだとき、母はどのような想いで写したのか胸を突かれた。
幼くて罪を知らず 胸に枕して むずかりては
手に揺られし 昔忘れしか
汝がために祈る母の いつまで世にあらん
永久に悔ゆる日の来ぬ間に とく神にかえれ
母は私の生き方をいつも励ましてくれたし、文を書く仕事をしているとき、いちばん喜んでくれていた。会えばいっしょにお祈りもして、電話で母の祈りを聞いてから私の一日が始まった。ただ、晩年の母の祈りには、私が人の評判を気にしたり、完成した本でも、その行く末を心配したりするのをやめるようにという思いが込められていた。
神さまから吹いてくる風に乗って、神さまが望まれるままに生きなさいとよく言われた。嫌なことが起こると、それはよい知らせだとさえ言った。そこから離れなさい、神さまに任せて待ちなさいと言った。改めて母の写した讃美歌の歌詞を読んで、私は神さまを信じていると思っているけれども、それはもしかすると自分の中にある偶像の神さまかもしれなかった。
母が私のために祈り続けてくれたのは、私が創った神さまではなく、真の神さまに帰れということなのだろう。母の死後、私は一度も泣かなかった。しかし、この歌詞を読んで、涙があふれてきた。それは私の命を育んでくれた母のぬくもりに包まれたからだ。