2019年07月05日の心の糧

父のぬくもり
シスター 山本 久美子
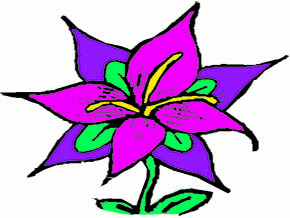
子どもの頃の私にとって、父親は、側にいるだけで緊張してしまい、側に近づけない恐い存在でした。ですから、私には、父との良い思い出があまりありませんでした。
教会に通うようになっても、神様を「父」と表現することで、より親しく神様を感じられることは私にはなく、むしろ厳格なイメージにつながり、ピンと来ませんでした。
聖書のルカ福音15章に、有名な「放蕩息子」のたとえ話があります。その話を初めて聞いた時、私は、自分の父親とは全く違う、父なる神のイメージにショックを受けると同時に、毎日、断腸の思いで子どもの帰りを待ち続ける父親の姿に、無条件で子どもを喜んで迎え入れる深い愛に、心からの飢え渇きを覚えました。ふり返ると、私のこれまでの信仰の歩みは、この私を無条件に愛し、待っていてくださるそんな大きな存在に巡り会うための憧憬と探究の道のりでした。
やがて、私も、祈りやいろいろな経験を重ねて、「放蕩息子」に描かれる父・・・神様の深いいつくしみを、頭ではなく心や体で味わい、「父」なる神様に安心して信頼することを学んできました。
そして、一人の大人として、信仰の視点で、自分の父に対する思いを味わい、受け取り直す恵みをいただいたのです。
そのプロセスで、私は、父にとっては到底理解できない修道生活の道に進み、父の思いを顧みることが少なかった私を、父がどれほどの痛みの中で受け入れてくれたのか・・・という思いに至り、私に対する父の愛情にも気付かされたのです。今も、父との関係が全くスムーズになったとは言えません。しかし、父なる神の眼差しという「ぬくもり」の中で、恵みに変えられていくと信じて、委ねています。