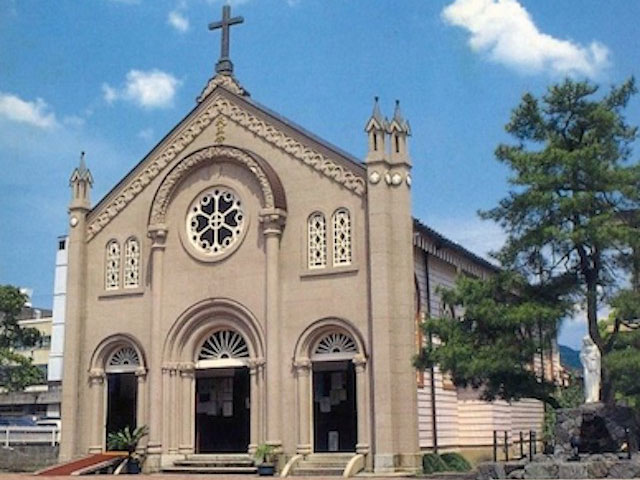=信仰を生きる= 教皇フランシスコの姿が、新聞やテレビで放映されるたびに「信仰を生きる」とは何か、その具体的生き方を教えられます。そこに見られる信仰とは、毎週...
キリスト教の歴史
明日の教会に向けて
小教区の現状と新しい共同体作りを考えるとき、私たちは次のことを理解し、行動に移さなければならないでしょう。 キリスト者であるということは、聖職者、修道者、一...
さて、従来からの課題とその改善は次の3つが考えられるのではないでしょうか。 ①教会のクレリカリスム(Clericalism:聖職者中心主義)からの脱却。 ...
新たな時代に向けて福音宣教していくためには、どうすれば信徒と聖職者が、時代を担う宣教を果たすために、お互いを刷新することができるだろうか。それはまず立場と職務...
まず、第二バチカン公会議以降、歩みはじめた日本の教会と使徒職の反省点から考えていきます。 第二バチカン公会議後26年が過ぎた頃、日本の教会は、ようやく公会議...
35年前、まだバチカン公会議後の活動が活発に行われていた頃、筆者は信徒使徒職について論文を書きました。その論文の中で「明日の教会の姿」と題して記した箇所を思い...
この総集編を書き下ろすにあたり、はじめに現在日本の教会を取り巻く様々な問題点を取り上げました。しかし、現状はこれらの問題以外にも山積していると思います。ここで...
③の段階:20世紀に入り、益々信徒の活動が活性化する。19世紀の信徒使徒職的な団体活動に加え、ピオ11世が推奨し振興した、位階制度的使徒職へ信徒が参加する「カ...
「信徒使徒職に関する教令」の締めにあたり、カトリック教会の歴史の中で開催された公会議は、なぜ開催されたのかを衆知しておく必要があるでしょう。何故ならいつの時代...
『信徒使徒職に関する教令』 終わりに; 第二バチカン公会議は、時代と共に移り変わる使徒職について論じられたのではなく、望ましい使徒職、つまり、初代教会において...