05月03日の教会の祝祭日

聖フィリポ使徒 聖ヤコブ使徒
聖フィリポ使徒
フィリポは、ペトロやアンデレと同じガリラヤのベトサイダ生まれで、ヨルダン川の岸辺にいたところ、イエスに従った最初の弟子の一人である。また彼の友人であったバルトロマイ(ナタナエル)をイエスの元に連れていき、バルトロマイも弟子に導いたことでも知られている。そうした事から12使徒の中で交際上手な人だったと言われる。福音書では、フィリポについて少ししか記されていないが、イエスを始め弟子たちとも親しく交わり、誠実で、現実的な人であったことが伺える。
その代表的な福音箇所が、イエスのパンの奇跡の場面である(ヨハネ6:7)。またイエスに「主よ、私たちに御父をお示し下さい・・」と言ったのもフィリポでした。度々福音の中でイエスに諭される箇所がありますが、彼の真理に対する探究心からであったと考えられている。彼のその後の活動は、ギリシャ、小アジア、ウクライナ、そしてトルコで宣教し、異教徒に捕らえられ殉教したと伝えられていれる。
聖ヤコブ使徒
ヤコブと呼ばれた使徒は、12使徒の中に二人いる。今日のヤコブは「アルファイの子ヤコブ」であり、もう一人のヤコブと区別するため"小ヤコブ"と呼ばれている。また一説によると彼は、イエスの従兄弟であったと伝えられるが、それは大ヤコブの方で、イエスと親戚だったと言われる。小ヤコブは、マタイの従兄弟説の方が確からしい。非常に信仰心が厚く、敬虔な人であった事から、ペトロの後を継承したエルサレム教会の初代司教であったと伝えられる。
彼は大勢の人々から尊敬され、多くの人を信仰へ導いたが、その為にファリサイ人から反感を受け、石打にされ殉教したと伝えられる。そして彼の遺体は、エルサレムの神殿の傍に葬られたと言い伝えられる。
05月12日の教会の祝祭日
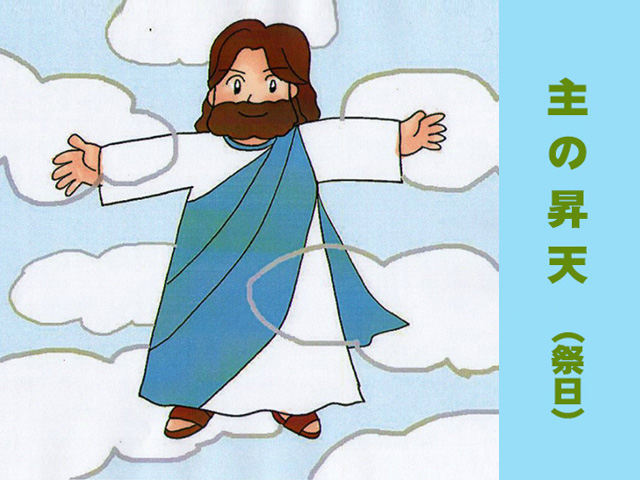
主の昇天
今日は「主の昇天」の主日です。ご復活後の40日目に、この昇天の祭日を祝います。ところがこの祭日は、必ずしも特別な休みの日として守るべき祭日でないとのことで、キリスト教国でない日本では、「主の昇天」の祭日を復活節第7主日にお祝いしています。
今日のイエスの主の昇天の出来事は、今日までのイエスの受難、死、復活、そして昇天、そして聖霊降臨へと続く、まさに焦点なのです。つまり、弟子たちとイエスの関係が一つの転機を迎えて、新しい聖霊の派遣というプレリュードだからです。それはまたイエスの残した共同体(教会)活動の黎明を告げているのです。
この昇天の出来事の意味は何か。言うまでもなくキリストの生涯の完成であるのと、"教会活動の始まり"のしるしでもあると言われています。弟子たちは、イエスから受けた命令に対して使徒活動を実践することで、後にイエスの教会が構築されていくその始まりなのです。それはまた生前のイエス・キリストから、復活後の聖霊降臨へと継承されていくのです。
聖パウロは、この出来事は非常に重要であることが、彼の書簡からも伺えます。その理由は、この昇天の出来事により、弟子たちも、そして洗礼の恵みに預かった者も、イエスから受け継いだ使命、その使命がキリストの使命と結ばれているからです。イエスの昇天は、聖霊による普遍の根源であり、それは世界のあらゆるところに普遍的に存在することによって、人類全てが、神の子に対する信仰と理解において一つのものとなり、成熟した人間になり、イエス・キリストの望まれる人に成長するからです。とパウロは書簡で伝えています。
05月14日の教会の祝祭日
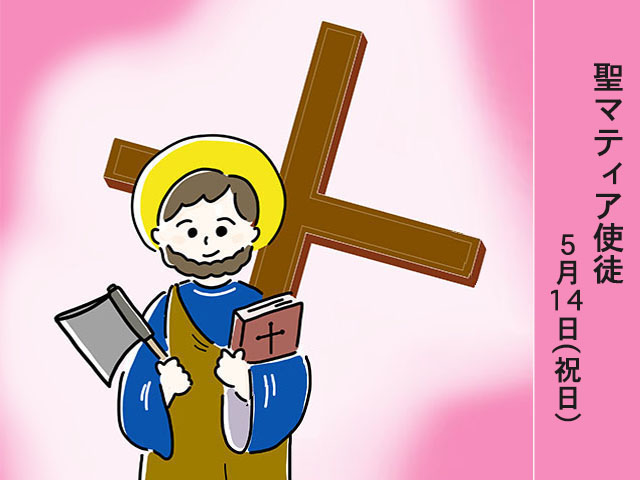
聖マティア使徒
「ユダが自分の行くべきところへ行くために離れてしまった、使徒としてのこの任務を継がせるためです。2人のことでくじを引くと、マティアに当たったので、この人が11人の使徒の仲間に加えられることになった」(使徒言行録1:25-26)。イエスの弟子であった12使徒の一人、イスカリオテのユダがイエスを裏切った。そこでペトロをリーダーに他の使徒たちは、その後任を2人の候補者バルサバと呼ばれユストとも言われたヨハネとマティアから選ぶことにし、くじを引いた結果がマティアであった。
使徒が、11人のままでは不完全であるというのは、使徒たちをイスラエルの十二部族の代表と考えられていたことからだと考えられます。彼の名前が聖書の中で記されているのは、この箇所だけです。さらに、彼についての記録は、ほとんど見当たりません。ただ最初からイエスの弟子で、ユダヤ人、ベツレヘムで身分の高い家柄に生まれ、律法や預言書に精通し、人徳のある人であったと伝えられています。
その後マティアは、エルサレムからエチオピアまで宣教し、エチオピアで殉教したと伝えられていますが、一説によると63年頃、エルサレムでユダヤ人によって殺害されたとも言われています。
05月19日の教会の祝祭日

聖霊降臨
聖霊降臨Pentecostesペンテコステ(ラ)は、イエスの復活・昇天後、集まって祈っていた12人の使徒たちの上に、神からの聖霊が降ったという出来事のこと、およびその出来事を記念するキリスト教の祝祭日です。宗派によってそれぞれ言い方は異なり、聖霊降臨、五旬節、五旬祭、7週の祭りとも言われます。
聖霊降臨の日を、新約聖書の中で「五旬祭(ペンテコステ)」(使徒言行録 20:16)と記しています。旧約聖書では「初物の日7週祭」(出エ 34:22、民28:26)とも呼ばれ、もともとは収穫祭でしたが、エジプト脱出つまり過越から50日目に結ばれたシナイ契約を記念する日となったと言われます。キリストの復活を祝う50日目に復活節の終宴として、聖霊降臨を祝います。
主の昇天を見守った弟子たち、彼らが主の復活の証人としてその使命に派遣される為には、聖霊を受ける時間が必要でした。弟子たちは聖霊の息吹により、神のはかりしれないご計画を悟り、それはやがて確信へと移ります。この確信こそイエスが望まれた教会誕生の源であり、福音宣教の原動力になるものです。したがって、福音宣教する者は、自己の力に頼ることではなく、福音宣教をすべての民にのべ伝えるためには、どうしても聖霊の力が必要となるでしょう。
教会では、聖霊降臨を毎年記念することで、一人ひとりが聖霊の賜物に預かっていることを意識します。そして、一人ひとりは生きとし生けるものの教会との一致の根源に立ち返り、この日、真に新たにされることに気づく時なのです。聖霊の働きによって、霊の実が見える教会共同体として成長しているか、そうあるべき姿を新たに求められている日でもあリます。聖パウロは、「霊の導きに従って歩みなさい」(ガラ5:16)と言い「肉の望むところは、霊に反し、霊の望むところは、肉に反するからです」(ガラ5:17)と。そして「霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です」(ガラ5:22-23)と言っています。
05月26日の教会の祝祭日

三位一体
「三位一体」の言葉を一般の方が、使われる時「ちょっと本来の意味と異なっている」と思います。キリスト教の教えでは「本質(実体)として唯一である神が、父と子と聖霊という三つの区別された位格(自立存在、ペルソナ)である。それは万物を超越する神は自らを自由に人間に譲与する(神の自己譲与)。即ち、神である御子が父なる神によって遣わされて人間となり、神の愛を掲示し、神と人類を一致させる。・・・ 」と言われます。(P.ネメシェギ師)。
教会の"三位一体"説は、難しい教えの最高峰と言われています。聖霊降臨の主日の翌月曜日から教会暦では「年間」に入りました。年間に入った最初の主日が、三位一体の主日としたその理由は、次のことからでした。
教会は、イエスがご自身の生涯をかけて、神の使命を全うされた救いの業を思い起こし"父、子、聖霊"この三位が人類の救いを実現されたことを、もう一度味わい直すこと。なぜなら、三位一体の神秘は、人知をはるかに超えるものであり、決して解析し理解するものではないからです。そのことを教えてくださったのが、イエス・キリストでした。教会はイエスが教えてくださった神をできるだけ忠実に表そうとして、歴史の中で「三位一体の神」というキリスト教的な神理解が明確になっていきました。イエス・キリストは、私たちに三位一体の神秘を啓示し、さらに私たちを三位一体の中に招き、導いてくださるのです。
8世紀半ば頃から教会は「三位一体」のミサを捧げて来ました。また教皇ヨハネ22世は、1334年に三位一体の祝日をカトリック全世界の祝日と制定されました。そこからカトリック教会では、この三位一体の祝日を大切に伝えています。キリスト信者の人々にとって「父・子・聖霊」の名によって洗礼を受けたこと、そして毎日額に十字を切る度「三位一体」のうちに招かれていることに気づかせて戴きましょう。
05月31日の教会の祝祭日
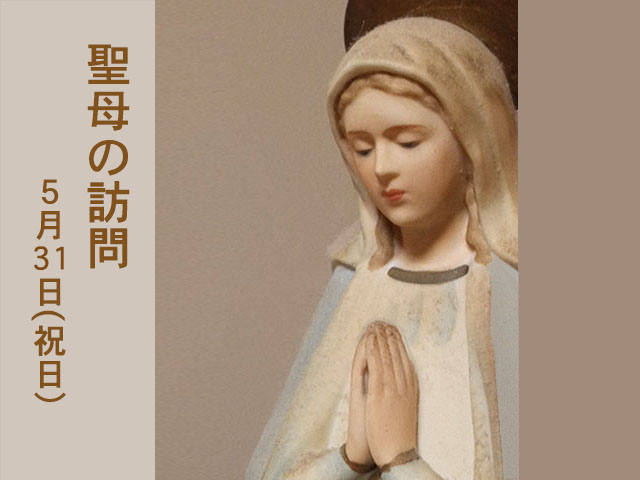
聖母の訪問
聖母マリアの祝日は多い。その中の一つ「聖母の訪問」は、マリアが天使ガブリエルからお告げを受けた後、不妊の女と言われ歳をとっていたが、もう六ヶ月になる男の子を身ごもっていた。今日はマリアが、ユダの町に住むザカリアの妻である親類のエリザベトを訪問したことを記念する日です。訪問してくれたマリアと出会ったエリザベトは、マリアに向かって「あなたは女の中で祝福された方です。胎内のお子様も祝福されています。わたしの主のお母様がわたしのところに来てくださるとは、どういうわけでしょう......」と感激、感動して心の底から出てきた言葉を伝えます。
このエリザベトの言葉を聞いたマリアは、エリザベトの最後の語句「神がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう」の言葉に確信を得たのでしょう。エリザベトとともに心から神に感謝し、その言葉に励まされ神へ賛美した祈りが有名な「マニフィカト」(マリアの賛歌)です。「わたしの魂は主をあがめ、わたしの霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです。......」(ルカ1:46~55)
このマリアのとった行動・エリザベト訪問は、身ごもっていたエリザベトの出産前の準備を手伝うためであり、それは神と隣人への愛のしるしでもあるのです。今日の祝日は、その意味でただお祝いすることだけでなく、助けを必要としている方へあなたも愛の実践を心がける日でもあるのです。