「心のともしび」ホームページを訪れてくださる皆様へ
2026年02月のお便り
ラジオを聴きながら
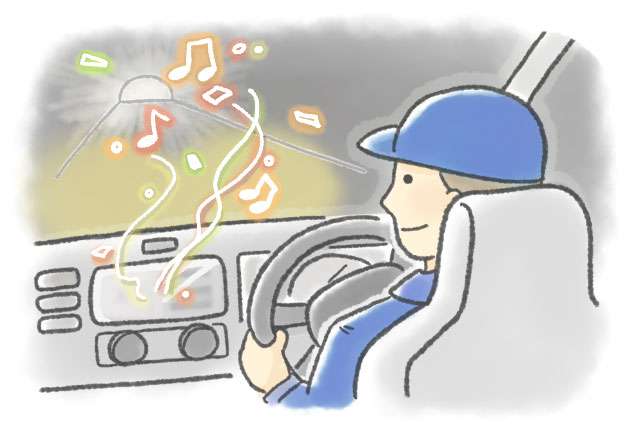
2月が寒さのピークとよく言われますが、まだまだ厳しい毎日、どうか対策を十分にしてお過ごしください。
寒さは厳しいのですが、日差しは一日一日強くなってきていて、春を思わせる陽気を感じることもあります。
春を思うといえば、4月刊行予定の「心のともしび」復活祭特別号の印刷がすでに出来上がってまいりました。
この特別号のために、東京大司教区の菊地功大司教さまからご寄稿いただき、第一面に掲載させていただきました。また、これを機会にと近隣のミッションスクールに購読を呼び掛けたところ、複数の学校から4月の復活祭特別号の購読や機関紙の年間購読をお申込みいただくことができました。
幼稚園や中学・高等学校でご購入いただいている機関紙は、児童、生徒ばかりでなく保護者の方も手に取ってくださっているようです。時々、思わぬ方から「お名前を心のともしびで拝見しました」と声がかかります。
ラジオ番組「心のともしび」も早朝の長寿番組として定着していますが、いったいどんな方が早起きして番組を聴いてくださっているのだろうと思っていました。
最近になって、早朝からお店の準備をされている方や長距離トラックのドライバーの方が、仕込みや運転の最中に耳を傾けてくださっていることを耳にしました。確かに、ラジオなら聴きながら仕事や支度ができますので、朝の時間の習慣にしておられる方も多いようです。
こんなお声やお話に触れるたびに、「心のともしび」のささやかなメッセージが、広く一般の方へも思わぬ形で届いているのだなと感心します。
ネット環境におられる皆様の中には、SNSやポッドキャストなどのツールもお使いになってお聴きくださっているかと思います。
これからも、聞いてくださる方や読んでくださる方の心に残るメッセージをお届することができるよう、執筆者の方と力を合わせて歩んで参ります。
*ホームページ「心の糧」2月のテーマは「心おだやかに」です。どうぞご視聴ください。
心のともしび運動 奥本 裕