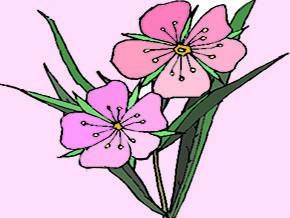「悔い改める」という、この言葉には、なにか、大変深い重みを感じます。「悔いる」こと、そして「改める」こと。いずれも、そこには、なんらか、人生の行き詰まりや悩みが...
2018年06月の心の糧
イエス・キリストの「先駆者」と呼ばれた洗礼者ヨハネは、人々の「あなたはどなたですか」という問いかけに「私は荒れ野で叫ぶ声である」と答えました。(ヨハネ1・19)...
かつて日本聖公会の教会を訪れて、カトリック教会のミサに当たる聖餐式に与ったことがありました。カトリック教会の主日ミサと共通する所がたくさんあって、嬉しくなったこ...
わたしたちは、弱い人間ですから、どんなに才能があっても、失敗することがあります。そのたびに、七転び八起で、失敗は成功の基なり、と前向きの考え方をして立ち上がれば...
自分はこんなにも怒りっぽかったのかと自覚したのは、大学卒業後、小学校の教師になったときでした。授業中に子どもたちが騒がしいと、大声で怒鳴りました。言うことを聞か...